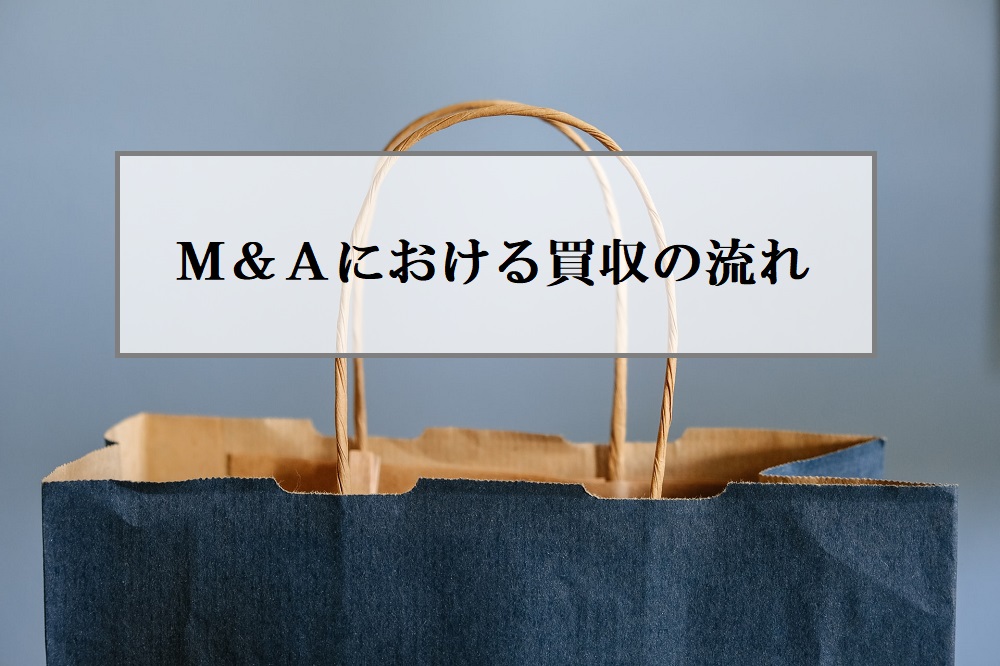M&Aの手法や言葉の意味について調べてみたけど、具体的な流れがわからない。
買収側のイメージが浮かばない。
そういった疑問、あるかと思われます。
この記事では、現役M&Aブティックファーム社員である私が買収の流れについて解説します。
M&A業界への転職を考えている方、M&Aにおける買収の流れについて理解を深めたい方に読んでもらえれば幸いです。
売却についての流れは下記の記事で詳しく書いているので、ご参照ください。

「売上数百億程度の事業会社」による買収を前提に進めていきます。
では、早速見ていきましょう。
会社を買収する際の流れ
会社を買収する際は、以下の流れでM&Aを進めます。
- 事前検討
- 交渉
- 実行
事前検討フェーズで「どこから、どんな経営資源を手に入れるか」を決めていきます。
交渉フェーズでは「いくらで買えるのか、どの会社を買うのか」を決め、基本合意を締結しデューデリジェンス(通称:DD)を行い買うことにより発生するリスクを洗い出します。
実行フェーズではDDで洗い出されたリスクの対処を組み込み、詳細な買収条件を決定、買収を実行。取得した事業・会社と自社の統合を行います。
売却側はここで話が終わりますが、買収側はここからがスタートです。
買収価格以上の価値を生み出すことによって、やっとM&Aが「成功した」と言えるでしょう。
事前検討
事前検討のフェーズで売手がやるべきことは、以下の通りです。
- 買収戦略の立案
- ロングリスト・ショートリストの作成
- 売手との接触
買収戦略の立案
買収は手段であり、M&Aによる買収そのものが目的ではありません。
ほしい経営資源(工場・優秀な人材・販路等)・事業領域は一体なにか。その経営資源・領域を抑えることでどういったことが期待できるのか。
既存事業の強化に使うのか。はたまた商流のカバー出来てない部分を補完するのかと目的は様々です。
自社にとっての課題、買収するべきか否かを洗い出し対象企業(売手)の選定へ移ります。
ロングリスト・ショートリストの作成
ロングリストは十数社~数十社の売手候補先がまとめられたリストになります。
自社、もしくは買手側につくFAや仲介会社に依頼し買収領域、エリア、規模感等の条件をもとに作成します。
https://www.bolzoiblog.com/wp-admin/customize.php?url=https%3A%2F%2Fwww.bolzoiblog.com%2Fmabaikyakunonagare%2F
この中から本当に買収しても良い良質な会社のみを絞り込みます。
厳選されたリストを「ショートリスト」と呼び、M&A会社はこのショートリスト先に接触を試みます。
既に取引のある会社を買収する際はこのようなリストは使わず、そのまま相対で交渉することもあります。
売手との接触
ショートリストを基にM&A会社は紹介、DM、コールドコール等の手段を使い売手先へコンタクトを取っていきます。
売却の意向、IMといった企業概要書、売手・買手によるトップ面談。
これらを経て売手の売却意思や希望をヒアリングしていきます。
交渉
売手と接触し、売却の意向が見えてきた段階で検討から交渉へステージが移行します。
- 買収価値の試算
- 基本合意の締結
- デューデリジェンスの実施
買収価値の試算
買手は買収したい企業・事業の買収価値を試算します。
買手は売手の情報を限定的にしか取得できない上に、事業シナジー込の価格を見込むため試算は困難です。
後に行うDDによって試算は正確になっていきますが、現段階では正常と思われる価格とズレが発生します。
ここで大体の価値を試算し、買収コストを計算。買収意向を示す基本合意を売手と締結します。
基本合意の締結
基本合意書は買手と売手の交渉内容を文書に落としたものになります。
LOI(Ltter of Interest)、MOU(Memorandum Of Understanding)という略称で呼ばれることもあり、基本合意書には以下のような条件が記されます。
- 売却価格
- 取引の手法
- スケジュール感
- デューデリジェンス対応について
- 独占交渉権
法的な拘束力はなく、基本合意を締結したからといって買収が確約されたことにはなりません。
相対ではなく入札形式の場合は複数社が一社に対して意向を出すこともあり、価格が吊り上がることも珍しいことではありません。
この後のデューデリジェンスや予想外の事態によって想定以上のリスクが発覚した場合、買収そのものを中止するということもあります。
M&Aにおける買収は企業価値を向上させる手段であり、目的ではないため勇気ある撤退も必要になるでしょう。
デューデリジェンスの実施
基本合意締結後、対象会社への詳細なデューデリジェンス(通称:DD)を行います。
DDは投資対象である事業内容・経営実態を詳しく調査・検討する作業です。
DDでは財務・税務・法務等の面から「リスクの洗い出し」「買収条件の調整」「経営統合で起こりうる課題の発掘」を行い、ほんとうに適正な価格で買収できるのか。買収したとしてうまく統合・事業シナジーを生み出せるのか明らかにしていきます。
特定のFA・証券会社にお願いする事業会社もあれば、案件の度に各会社に依頼する企業もあります。
費用は数百万~数千万円かかることがあり、買手にとって非常に骨の折れる実務の一つと言えるでしょう。
無事DDが終わり、リスクを洗い出した後は実行フェーズへ移行します。
実行
最後に、実行フェーズへ移ります。
- 買収契約の締結
- クロージング
- PMIの実施
DDで出てきたリスクへの対応・交渉結果を文書に落とし売手と売却契約を締結。クロージングという流れになります。
売却契約書はDA(Definitive Agreement)。株式譲渡の場合SPA(Stock Purchase Agreement:株式売買契約書)という略称で呼ばれることもあります。
SPA、売却契約書には以下のような要素が盛り込まれます。
- 売主の表明保証
- クロージング実行の条件
- 株式譲渡等の合意
無事に契約成立、買収終了です。
最初に述べたように、買収側はここからがM&Aのスタートです。
PMI(Post Merger Intergration)という買収先との統合プロセスを実施。企業文化、従業員の意識、販売体制、管理体制等を調整していきます。
企業価値向上を図り、買収価格以上のリターンを得るための活動を開始します。
買った以上の価値を買収先会社との連携で生み出し、はじめてM&Aが成功したと言えるでしょう。
おわりに
以上が、M&Aで会社を買収する際の流れについてでした。
買収の流れについて理解を深めることで、M&A会社の行っている業務へのイメージや買収側の課題・目的が明らかになってきたのではないでしょうか。
買手側はバイサイドと言い、事業会社だけでなくファンドもバイサイドプレーヤーの一種です。
ファンドのホームページにある投資実績・支援内容から具体的な投資事例が見れるため、より理解を深めたい方は是非チェックしてください。
事業会社のM&A戦略についてはホームページの「IR情報」にある中期経営計画や決算説明会資料に記されています。
https://www.bolzoiblog.com/wp-admin/customize.php?url=https%3A%2F%2Fwww.bolzoiblog.com%2Fmabaikyakunonagare%2F
各社の経営戦略やM&Aについての考えを知っておけば、面接で話題にもできますし当事者意識も高まります。
M&A業界への転職を考えられている方は、是非多くのホームページを訪問し自分なりの考えを構築してください。
転職活動だけでなく、無事に転職を成功された後も役に立つことでしょう。