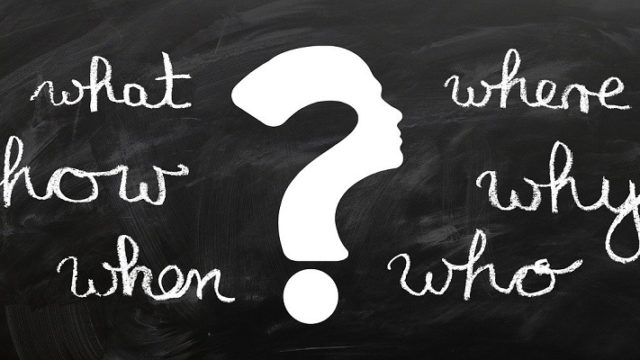M&Aで会社が売却される際の流れがイメージできない。
M&A業務でいったい何をやるのか想像がつかない。
そのように考えた転職者の方、多いのではないでしょうか。
安心してください。
M&Aの流れは一見複雑ですが、分解して部分ごとに見れば理解は可能です。
この記事では、現役M&Aブティックファーム社員である私が売却のプロセスについて解説します。
M&Aの流れについて理解を深め、M&A会社の具体的な業務イメージを持つ一助にしてください。
買収における流れについては下記の記事で解説していますので、ご参照ください。

「60歳、独身、飲食店複数経営、売上高10億程度、未上場企業の経営者」による売却を前提に話を進めていきます。
では、早速見ていきましょう。
会社を売却する際の流れ
会社を売却する際は、大きく以下の流れでM&Aは進んでいきます。
- 事前検討
- 交渉
- 実行
事前検討フェーズで「いつ、だれに、どうやって売るのか」を仲介業者orアドバイザリーと相談し、買手と接触。
交渉フェーズでは「いくらで売れるのか、誰からの誘いを受けるのか」を決め、デューディリジェンス(通称DD)という買収側からの企業調査の対応を行います。
実行フェーズではDDで洗い出されたリスクへの対応を文書におとし、詳細な売買条件を決定、売却を行います。
仲介とアドバイザリーの違いについては、こちらの記事をご参照ください。
事前検討
事前検討のフェーズで売手がやるべきことは、以下の通りです。
- 売却目的について考える
- 売却時期の検討
- 誰に売るかの検討
- ロングリスト・ショートリストの作成
- 買手との接触
売却目的について考える
売却は手段であり、M&Aによる売却そのものが目的ではありません。
今回は売手経営者が高齢・独身であることから「事業の承継が困難」という問題が発生しています。
これを解決するのがM&Aで、今回の売却目的は「売却による事業存続」になりますね。
売却時期の検討
次に、経営者はいつ売るかの検討に入ります。
M&Aの取引は一般的に3~6ヶ月かかると言われており、1億程度の小粒な案件でもない限り長期戦です。
すんなり数ヶ月で決まれば良いものの、取引が成立せずにまた買手を探し直すこともあります。
もし売却を現実的に検討しているのなら、早期の売却に向けた動き出しが重要になってきます。
誰に売るかの検討
経営者にとって事業は手塩にかけた我が子のようなものなので「誰でもいいから売りたい」とはなりにくいです。
事業会社に売るのか、ファンドに売るのか、買収先の経営資源はなにか、自社とどんなシナジーが生まれるのか。
この検討が不十分だと、買収先はうまく会社を扱えず、売手オーナーももどかしい思いをし当事者全員が不幸になります。
そのようなリスクを極力減らすため、M&A会社はオーナーに対しコンタクト予定の会社をリスト化して事前に渡します。
十数社~数十社の買手候補会社が記されたリストを業界では「ロングリスト」と言います。
ロングリスト・ショートリストの作成
ロングリストは多くの買手候補先がまとめられたリストになります。
売手オーナーとのディスカッションを経て、A社になら売却を考えても良い、B社はカルチャーが会わないから駄目。
といったふうにコンタクト先を絞り、本当に買収されても良い良質な会社のみを絞り込みます。
厳選されたリストを「ショートリスト」と呼び、M&A会社はこのショートリスト先に接触を試みます。
買手との接触
ショートリストを基にM&A会社は紹介、DM、コールドコール等の手段を使い買手先へコンタクトを取っていきます。
売却の意向、シナジー説明、売手・買手のトップ面談。
これらを経て買手の意思や希望をヒアリングしていきます。
交渉
買手と接触し、買収の意向が見えてきた段階で検討から交渉へステージが移行します。
- 売却価値の算定
- いくら残るのか試算する
- 基本合意の締結
- デューデリジェンス対応
売却価値の算定
ここで売却が現実的になってくるので、株式価値を明らかにしていきます。
町の会計士、監査法人、証券会社、独立ブティックファーム等の算定期間へ依頼し、売却価値をわりだします。
算定機関による精緻な株式価値を知ることでオーナーには現実がつきつけられます。
サンプル数は数十社ですが、自社株式価値を高めに見積もるオーナーは多く、この結果に納得いかず売却をやめるパターンもあります。
いくら残るのか試算する
会社の売却によって得られるキャッシュ、そこから引かれる税金・M&A会社等に払う手数料を試算します。
この仮定を経るとオーナーの目線は安定し、やけにブレるということはなくなります。
価格の目線を決めた後は基本合意の締結に進んでいきます。
基本合意の締結
基本合意書は買手と売手の交渉内容を文書に落としたものになります。
LOI(Ltter of Interest)、MOU(Memorandum Of Understanding)という略称で呼ばれることもあり、基本合意書には以下のような条件が記されます。
- 売却価格
- 取引の手法
- スケジュール感
- デューデリジェンス対応について
- 独占交渉権
法的な拘束力はなく、基本合意を締結したからといった安心はできません。
この後のデューデリジェンスや予想外の事態によっては余裕で取引が破談、ブレイクします。
帰るまでが遠足。フィーが入金されるまでがM&Aです。
デューデリジェンス対応
基本合意締結後、買手による詳細なデューデリジェンス(通称:DD)が行われます。
DD対応中も企業の活動は続くため、売手は事業を進めながらDD対応に追われることになります。
買手は税務・財務・法務等リスクを洗い出すため資料請求・質問を雨あられと売手へぶつけます。
セルサイドのFAは質問の交通整理等を行いオーナーによるDD対応の負担を減らしていきます。
無事DDが終わり、リスクを洗い出した後に実行フェーズへ移行します。
実行
売却成立まであと少しです。
最後に、実行フェーズへ移ります。
- 売却契約の締結
- クロージング
DDで出てきたリスクへの対応・交渉結果を文書に落とし売却契約を締結。クロージングという流れになります。
買収契約書はDA(Definitive Agreement:)。株式譲渡の場合SPA(Stock Purchase Agreement:株式売買契約書)という略称で呼ばれることもあります。
SPA、売却契約書には以下のような要素が盛り込まれます。
- 売主の表明保証
- クロージング実行の条件
- 株式譲渡等の合意
無事に契約成立、売却終了です。
売却側はここでキャッシュを受け取り終了となります。お疲れ様でした。
おわりに
以上が、M&Aで会社を売却する際の流れについてでした。
売却の流れについて理解を深めることで、M&A会社の行っている業務へのイメージも深まってきたのではないでしょうか。
事前準備までが「ソーシング業務」、交渉~実行を「エグゼキューション業務」と言い、求められる人物像も変わってきます。

M&A業界についての知識をつけ、転職で有利に立ち回っていきましょう。